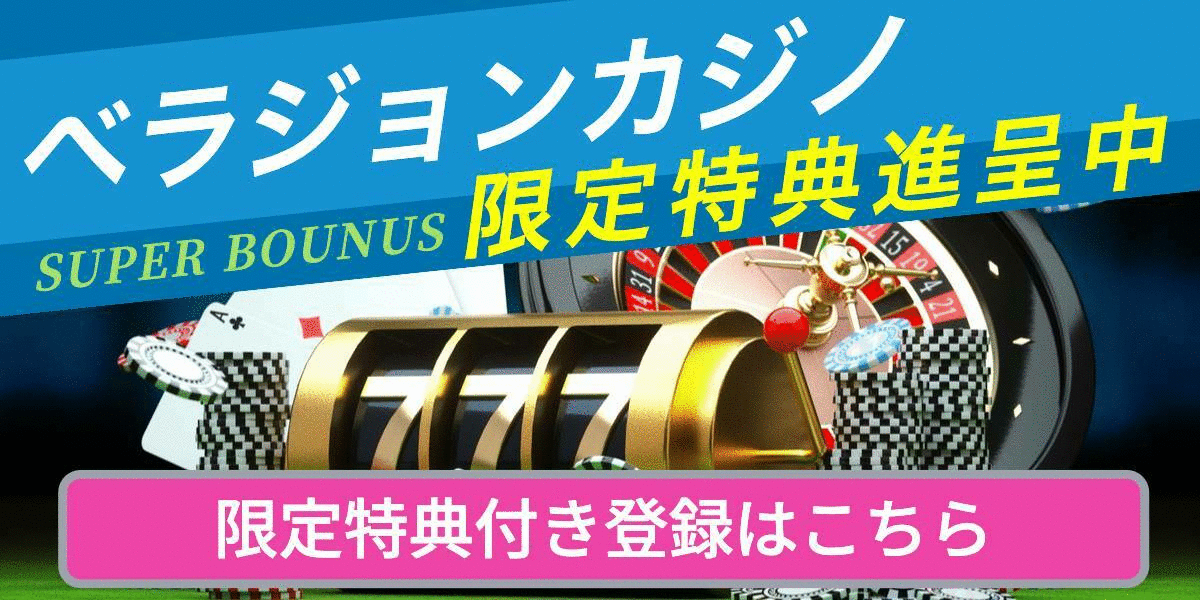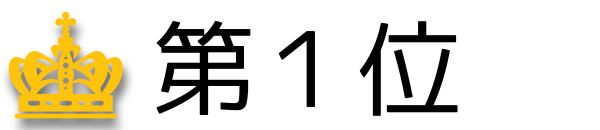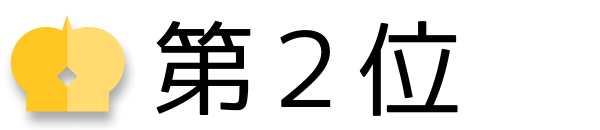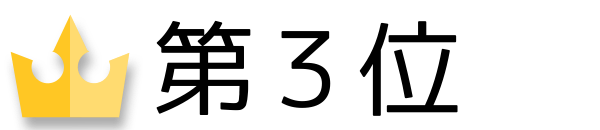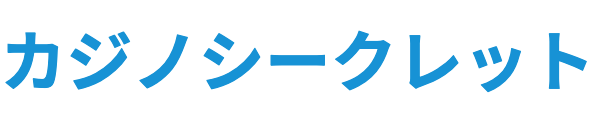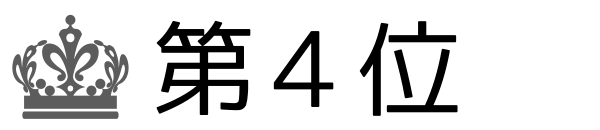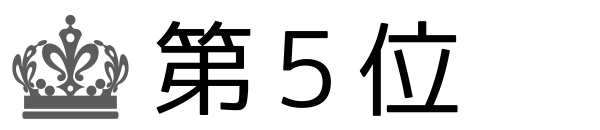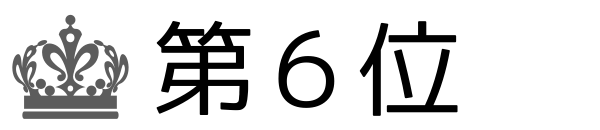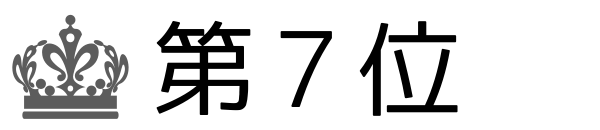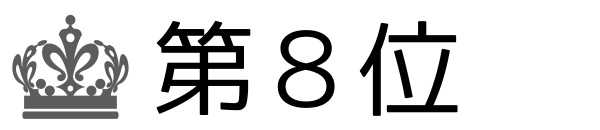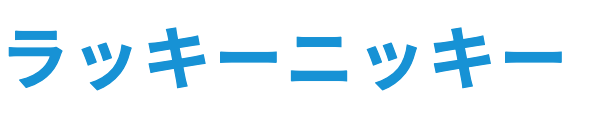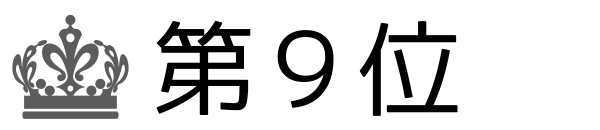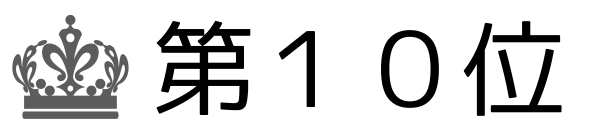https://www.youtube.com/watch?v=Q_XQV-owbpU
■■■今回の一言■■■
個人的にはこのシリーズが一番好きです。
連日満員御礼!!目指せ月収100万円!!
■■■イキナリデンキ大学■■■
◆エアコンのトラブルはイキナリデンキ◆
LINEで電気工事士に相談ができて安心!もちろん相談費用は全て無料!
【不動産提供したい】【エアコンの講師したい】【海老澤と働きたい】
という物好きな方は下記のSNSへ直接連絡ください。
(会社に電話してこないでください笑)
■■■海老澤の日常と会社■■■
ウバジのぼやき
海老澤のインスタ
海老澤のフェイスブック
株式会社あそこのHP
自称日本一の運動会屋さん
【ガチ有料級!】焼き鳥で独立開業するなら絶対見るべし!
@ミスター月山のやきとり大学